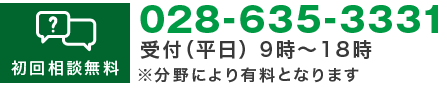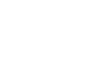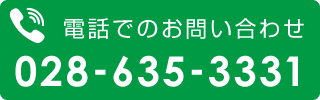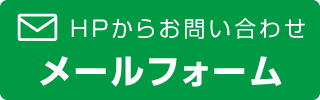Author Archive
【ブログ】弁護士の仕事道具1(キーボード)
弁護士の小坂です。
私は大学を卒業するまでほとんどパソコンを使ったことがありませんでした。
パソコンを起動したり、シャットダウンしたりすることすらできず、それをいとも簡単に操作している人を見てすごいなぁと思っていた遠い記憶があります。
そんな私も大学を卒業して司法試験予備校でバイトをはじめました。それをきっかけにコンパック製のパソコンを購入しました。モニターはブラウン管、やたらと迫力のある音を出すJBLの外付けスピーカーが付属していて、キーボードもとても打ちやすかったように思います。
私は、ポストペットの打モモというタイピングソフトをひたすらやりまくりました。1か月程度でタッチタイピングができるようになり、その後も1年間毎日のようにタイピングソフトをやっていました。単にゲームとして面白かったからです。そのうち1秒間に何回打鍵できるかという当初の目的を逸脱した挑戦を開始していました。
そんなわけでいつしか文書を作るには困らないくらいのタイピング術を身につけました。その後、弁護士になってから、何時間もぶっ通しで書面を作成することが増えていきました。
そして私が出会ったのが、東プレのリアルフォースです。キーボードに関心がある人にとってはあまりにも有名な製品です。しかし、キーボードに興味がある人というのは世間的にはあまり多くないようなので、誰でも知っている製品というわけでもないようです。
いま東プレのサイトを見ましたが、自動車の外装部品をプレスしている動画が流れていました。キーボードを目当てにこのサイトに行き着いた人は一瞬サイトを間違えたかと思ってしまうかも知れません。が、ちゃんと電子機器関連製品としてキーボードも紹介されているので間違いではありません。
前置きが長くなってしまいましたが、もう私はずっとリアルフォースを使い続けるのだろうなというくらいこの製品に惚れ込んでいます。製品としての作り込み方がとてつもないレベルです。高価な品なのに、否、高価であるからこそ、今時にもかかわらず有線のキーボードです。本気度がうかがえます。リアルフォースの特徴、それは当然、スイッチ機構に「静電容量無接点方式」を採用していることです。なんだか凄そうですが、本当はよく分かっていません。先日、チコちゃんに叱られる!を見ていたらスマートフォンの画面にも静電容量方式が採用されていると説明されていました。私は、テレビを見ながら、「これはあれだ、リアルフォースのあれだ」と思いましたが、その感動を分かち合えるマニアな人は近くにいませんでした。技術的なことはさておき、打鍵感がなんともいえず心地よいのが特徴です。私は一番荷重の軽いタイプを使っていますが、とにかくぬたぬたとキーがなめらかにストロークします。どう表現すべきかわかりませんが、私にはぬたぬたということばがしっくりきました。
ロジクールの無線キーボードなんかを置いて机周りをすっきりさせたいと思ったりすることもありますが、キーボドから伸びていく無骨なコードもリアルフォースのよき個性と思えます。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【コラム】文書の成立の真性を争ったら過料に?
民訴法230条1項は、故意又は重過失で真実に反して文書の成立の真性を争った場合、10万円以下の過料に処せられることがあることを定めています。
文書の成立の真性とは、文書が本当にその文書作成者とされている人の意思によって作成されたかどうかという問題です。たとえば、文書を見るとAさんの署名があって証拠上もAさんが作成した書面として提出されているが、真実はBさんが作成した書面であるという場合、文書の成立の真性が認められないということになります。平たくいえば偽造文書かどうか争うというのが、文書の成立の真性を争うということです。
民訴法230条は、例えば代理人が「これは偽造じゃないのか?」といって文書の成立の真性を争ったが、裁判所は証拠上はそれは偽造じゃないと認定した場合で、「そんなのちょっと調べれば分かるでしょう?」というときはペナルティとして10万円の過料に処すこともありますよということを宣言している規定です。なんと、当事者のみならず代理人個人が過料に処せられることもあるという規定であり、もし裁判所から過料に処せられたら弁護士としてはかなり落ち込むだろうなと思います。
法律の趣旨は、訴訟遅延をもたらした者への制裁という意味があるようです。そして、当事者に真実義務を課している規定だとも言われているようです。
実際に民訴法230条によって過料に処せられる事例はほとんどないのだと思いますが、法律上の根拠がある以上、積極的に過料に処していく運用も可能なはずであり、もしそのよう運用がなされるとしたら、民事裁判にこれまでとは違った風を吹き込むことになるのではないでしょうか。それがよい風なのかは分かりませんが。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【検討-刑訴法1】保釈許可決定の執行停止申立ての法律上の根拠
【契機】
保釈許可に対して検察官が不服申立てを行った場合、執行停止の申立てが同時になされるようだが、この執行停止の法律上の根拠はどこにあるのか?
【検討】
勾留によって身柄の拘束を受けていた被疑者が起訴されると保釈請求をすることが可能になります。被告人が保釈を望む場合、起訴後すぐに保釈請求をすることになるでしょう。この保釈の可否は、当該事件の裁判を担当する裁判官以外の裁判官が判断するのが原則です。裁判官が保釈を許可する決定(ほんとうは命令)を下した場合、検察官がこれに対して不服を申し立てなければ被告人は釈放されることになります。
しかし、検察官が保釈許可決定に対して不服(準抗告)を申し立てた場合はどうなるのでしょうか。保釈許可決定が出ている以上、被告人はとりあえず保釈されるのでしょうか。その後、準抗告に理由があるとして保釈許可決定が取り消されたら、被告人はまた留置施設に入れられてしまうのでしょうか。せっかく釈放されたのにすぐまた身柄拘束を受けるというのもどうなんでしょう。
しかし、結論からいえば釈放されたり、すぐまた勾留されたりという事態はあまり発生しないようです。なぜなら、検察官は不服申立(準抗告)を行う際に、保釈許可決定の執行停止の申立ても行うからです。
刑訴法424条は、準抗告ではなく抗告に関する規定ですが、原裁判所(保釈許可決定を出した裁判所)も抗告裁判所(不服の審査を行う裁判所)も執行停止を決定できるということを明言しています。この執行停止決定は、裁判所が職権で行うものなので誰かの申立てがなくても裁判所の判断で執行停止とすることができるのですが、事実上、検察官が裁判所の職権発動を促すために執行停止の申立てをするということです。
この抗告に関する刑訴法424条は、刑訴法432条によって準抗告の場合にも準用されています。そのため、保釈許可決定に対する準抗告がなされた場合、刑訴法424条が準用する刑訴法432条によって執行停止となることが多いのだと思います(※2)。つまり、準抗告がなされた場合は、とりあえず被告人は釈放されないことになりますが、その後に準抗告が棄却されると執行停止の効力が失われて保釈許可の執行が可能となります。
ただし、準抗告棄却の決定に対して特別抗告がなされることもありえます。特別抗告というのは憲法違反、最高裁判例違反、大審院・高裁判例違反(※3)という3つのいずれかに該当する場合にのみ行える特別な不服申立てのことです。刑訴法434条により、抗告に関する執行停止を定めた刑訴法434条が特別抗告にも準用されます。その結果、特別抗告がなされた場合にも保釈許可決定の執行が改めて停止されることがあるということです。
【未解決の疑問】
裁判官が一人で行った裁判でも、裁判所として行った裁判はに対する不服申立ては、準抗告ではなく抗告によると考えられており、保釈許可決定に関する先例として裁決昭和31・6・13〔集14巻1号29頁〕が存在するとのことである。第1回公判前であれば公判担当以外の裁判官が保釈許可決定を出すのが原則とされているが(刑訴規則187条1項)、第1回公判前であっても一人の裁判官が裁判所として決定として保釈許可決定を下すことがあるのか。先の裁決を読めば分かるのかもしれない。
(※1)保釈許可決定に対して、抗告と準抗告の2種の不服申立てがありますが、その違いは簡単に整理すれば次のようになります。
第1回公判期日「前」→公判担当以外の裁判官が「命令」の法形式で保釈許可決定をする→「裁判官」が行った裁判(命令)に対する不服申立ては「準抗告」となる
第1回公判期日「後」→受訴裁判所が「決定」の法形式で保釈許可決定をする→「裁判所」が行った裁判(決定)に対する不服申立ては「抗告」となる
(※2)刑訴法432条は、抗告に関する規定が準抗告にも準用されますよということを定めている規定ですが、抗告の手続について定めた刑訴法423条は準用するとは言ってません。刑訴法432条は、抗告するなら抗告状を原裁判所に提出してくださいと定めていますが(1項)、準抗告の申立ては刑訴法429条1項によって準抗告申立書を原裁判所ではなく、直接に管轄の裁判所に提出することになります。そうすると、制度上は保釈許可決定を行った裁判官が準抗告が行われたことを法律上は知る立場にないことになります。すると、刑訴法は準抗告の場合の執行停止は、準抗告の当否について判断する裁判所(準抗告審裁判所)のみが判断することを予定しているのではないかという疑問が生じます。すなわち、抗告のように原裁判所(刑訴法424条1項)が自ら執行停止の決定をできるのかという論点が発生します。結論からいえば、準抗告の場合も、保釈許可決定をした裁判官が自ら執行停止の決定もできるというのが実務、学説のようです。
(※3)高裁判例違反は、新刑訴法施行以前に高裁が上告審としてした判決に関する判例のことです。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【コラム】熟年離婚の注意点
熟年離婚とは
熟年離婚とは、長い婚姻期間を経て離婚することをいいます。長い婚姻期間とは、だいたい婚姻20年以上を経た場合をいいます。このような熟年離婚は増加の傾向にあるようです。今回は、熟年離婚をする上で知っておくべき法律知識についてご説明いたします。
熟年離婚の理由・原因
熟年離婚の理由・原因は、さまざまですが中でも以下のような理由が多いのではないでしょうか。
- 性格・価値観の不一致
- 会話がない
- 長年にわたる侮辱
- 家事や介護に疲れた
法律上の離婚原因になるのか
熟年離婚であってもまずは、夫婦で話し合いをして合意ができれば、離婚届を作成して市役所に届け出ることで離婚が成立します(協議離婚)。この場合、離婚の原因が何であるかは問題になりません。しかし、協議離婚が成立しないと調停離婚を試みることになりますが、これも不成立となると裁判離婚によって強制的な離婚の成立を目指します。しかし、裁判離婚が認められるのは法律が定めている離婚原因が存在する場合に限られます。上記のような事情は、法律が定める離婚原因のうち「婚姻を継続しがたい重大な事由」への該当性が問題となります。上記は、いずれも主観的な評価が入りやすい事情であるため、客観的な証拠なしに一方の意見がそのまま採用される可能性は高くありません。また、程度としても、少しくらいの価値観の不一致では不十分と判断されることが多いのが実情です。これに対して、暴力、浪費、浮気等の外形的な事実・証拠があれば離婚原因の立証は比較的容易ですが、上記のような理由であることが多い熟年離婚では一般的に離婚原因を立証することに困難が伴うケースがあります。しかし、事案によっては、有力な証拠が存在する場合もありますし、丹念に主張・立証することで離婚原因が認められることは十分あり得ます。
大切なお金の問題
熟年離婚では、当事者は、「定年まであと数年」とか、「すでに定年して年金暮らし」というケースが想定されます。比較的若年で離婚したような場合であれば、自らが働いたり、再婚したりして自信の財産を築き直すことが可能ですが、熟年離婚の場合、そうした時間も機会も限られているのが一般的です。したがって、熟年離婚では、財産分与をはじめとした、すでに形成された資産の分配を受けることが非常に重要です。
財産分与
お金や資産の管理の方法はいろいろありますが、たとえば、貯金はすべて片方(夫名義又は妻名義)の口座に集約し、他方には全く貯金がないということはよくある話です。婚姻期間中に形成された夫名義又は妻名義の財産は、基本的に夫婦が共同で形成した実質的な共有財産とみるべきでしょう。そこで、離婚の際には財産分与といって、基本的に2分の1の割合で財産を分けるということが行われます。財産分与の対象となる資産は預貯金だけではなく、下記のとおり様々な資産が対象となります。それぞれについて、評価の方法など複雑な論点があるので財産分与が問題になりそうなら弁護士に相談するべきでしょう。特に熟年離婚の場合、退職金が高額になるケースがあるのでこれを対象に含めるかどうかによって分与額が大きく異なることがあります。財産分与は離婚から2年以内に請求しなければなりません。すでに離婚したという方は時期に注意してください。
- 不動産
- 預貯金
- 保険の解返戻金
- 株式
- 退職金
年金分割
熟年離婚では、婚姻期間が長期間に及んでいるため、年金分割の金額も大きくなる傾向にあります。年金分割は、条件を満たしていれば確実に得るとができるものなので分割によって年金額が増える側は分割請求することを忘れないように注意が必要です。離婚から2年を経過すると分割請求が制度上不可能となるので時期にも注意してください。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【ブログ】ホワイトボードと油性ペン
当事務所には会議室が2つありますが、どちらの会議室にもコクヨ製のホワイトボードが掛けられています。
複雑な事実関係や法律論をお客様に御説明する際に便利なのですが、実は自分の頭の整理にもすごく役立ちます。法律相談の最中もたまにホワイトボードに絵を書きながら考えたりしています。
ところで、私の執務室にも第三のホワイトボードがあります。これは引っ越し前の事務所から持ってきたもので、いわば創業時からの付き合いです。今はもっぱらTO DOメモとして機能しています。
先日、私は重要な作業を忘れないように赤いペンを使ってそのホワイトボードにメモを殴り書きにしました。もちろん、堂々とした、かつ、荒々しい書体で。。
後日、作業を終えたのでそのメモを消そうとしたときです。 あれっ!? イレーザー(黒板消しのようなもの)でこすってもびくともしない。。
うーむ。よく見るとこの赤い文字、とても光沢があるなぁぁ。。この艶、そしてこの存在感、これはホワイトボード用では出せませんよ!
・・・。
やっちまった。油性マジックで書いてしまった。改めて見てみると、この油性マジック、ホワイトボード用のそれとそっくりじゃないか。こだわって選んだ琺瑯製ホワイトボードガー。
しょうがないからこのままこのホワイトボードと付き合っていくしかないな。会議室のホワイトボードでなくてよかった。としょんぼりしながら思ったのでした。
ところが、ダメもとでネット検索してみたところ、油性マジックは消しゴムで消えるとの情報をゲット。ほんとにぃ?と思いつつ、さっそく消しゴムでこすってみると、ほんとに消えた!
少し根気が要るけど、消える。うっ、うれしい。
これは、私が最近一番嬉しかったことに関するお話です。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【コラム】新設された「刑の一部の執行猶予」について
<刑の「一部」の執行猶予の創設>
刑事法の分野で、「刑の一部の執行猶予」という制度が新たに創設されました。
本年6月までに施行されることになっています。
刑の一部の執行猶予制度とはどんな制度でしょうか。
昔からある刑の全部の執行猶予制度との違いは何でしょうか。
<刑の全部の執行猶予とは>
犯罪を犯した場合、懲役刑や禁固刑を科せられることがあります。
たとえば懲役2年の刑罰を科せられた場合、その刑罰が執行されると刑務所に収監されることになります。
しかし、懲役2年の刑罰を科せられても、それをすぐには執行しないことがあります。
これが刑の執行猶予というもので、たとえば「懲役2年、ただしその刑の執行を3年間猶予する」といった具合です。
判決が出ても刑務所に収監されることなく、家に帰してもらえます。
その後、新たな犯罪を犯さないで執行猶予期間(先の例では3年間)を満了すると、懲役2年という刑罰を執行されることはなくなります。
懲役2年という刑の全部について執行を猶予するので、刑の全部の執行猶予といいます。
これまでは、執行猶予といえば、制度上、刑の全部の執行猶予しかなかったので、わざわざ「全部の執行猶予」と呼んだりせずに単に「執行猶予」と呼んできました。
今回、一部の猶予という制度ができたので、これと区別するために、従前の執行猶予制度は、刑の全部の執行猶予と呼ぶようになりました。
<刑の一部の執行猶予とは>
刑の一部の執行猶予とは、先の例でいえば、懲役2年のうち、1年は刑を執行し、残り1年は刑の執行を猶予するというものです。
どうなるかといえば、まず、1年について刑の執行を受けるので、刑務所に収監されて1年間をそこで過ごすことになります。ただし、残り1年については、刑の執行を猶予するということなので、1年を経過すると刑務所から出所することになります。
2年の懲役刑を科せられたのに途中で刑務所から出てくるという意味では、仮釈放の制度と似ています。
<何がねらいなのか>
仮釈放の制度があるのに、わざわざ刑の一部執行猶予という制度を創設したのはなぜでしょうか。
一部執行猶予制度のねらいは、薬物犯罪者など再犯率の高い者に十分な保護観察期間を設定することにあります。
薬物犯罪者などの真の更生を図るためには、刑務所を出所した後、病院で治療したり、生活態度を改めたりする必要があります。
保護観察はそのお手伝いをする制度ですが、仮釈放制度下では、仮釈放された時点で残っている刑期しか保護観察に付せませんでした。
先の例でいえば、刑務所で1年を過ごした後、仮釈放で社会に出た後は、保護観察に付せるのは残りの刑期と同じ1年間だけです。
残りの刑期と同じ期間だけでは、その人に本当に必要なサポートが難しいのが実情でした。
刑の一部執行猶予の制度では、残りの期間がどうであるかにかかわらず、1~5年の間で必要なだけ保護観察に付せることができます。
薬物依存が顕著な人で、更生に困難が伴うことが予想される場合などは5年間の保護観察に付したりできるのです。
たとえば、懲役2年、ただし懲役2年のうち懲役1年(刑の一部)については5年間執行を猶予し、その5年の間保護観察に付するとした場合どうなるかといえば、次のようになります。
①まず、刑務所に収監されて1年間服役します。
②1年を経過すると刑の一部執行猶予の効果で出所します。
③出所後、5年間は保護観察によるサポートを受けながら社会生活を送ります。
④5年が経過すると保護観察が終了し、普通に生活することになります。
刑罰の重要な目的の一つに、その犯人が二度と犯罪を犯さないようにするということがあります(再犯の防止)。
これまでの刑事システムでは、薬物犯罪など一部の犯罪については、再犯の防止効果が不十分でした。
刑の一部執行猶予の制度は、再犯の防止のために創設された制度といえるでしょう。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【コラム】特殊な遺言の方式~死亡危急時遺言(臨終遺言)
死亡危急時の遺言とは
遺言にはいくつかの方式がありますが、病気などで生命の危険が迫っている場合に行うものとして死亡危急時遺言(臨終遺言)というものがあります。
死亡危急時遺言のやり方
1.死亡の危急にあること
遺言者に生命の危険が迫っていることが要件です。遺言者が危険が迫っていると自覚していればよく、必ずしも客観的な危険の存在が要求されるわけではありません。ただし、全く危険がないのに本人が危険だと思っているような空想の類いではこの遺言はできません。生命に関わる病気を患っており、その病状が悪化している等、ある程度、客観的な事情は必要だと思われます。
2.3人以上の証人の立ち会い
少なくとも3人の証人が遺言に立ち会わなければなりません。以下にあてはまる方は証人の資格がありません。たとえば、遺言によって財産を譲り受ける方や遺言者の子は、証人になれません。証人適格を欠く者は立ち会い自体を避けるのが無難です。
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③署名できない者(後記6を参照)
④遺言者の口授を理解できない者(後記3を参照)
⑤筆記が正確であることを承認する能力がない者(後記5を参照)
※証人・立会人の欠格事由は、民法974条各号に定められていますが、同条3号の「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」であることが欠格事由になるとの規定は、死亡危急時遺言のような特別方式による遺言には適用がありません。
3.証人の一人への遺言の口授
遺言者は、証人のうちの一人に口頭で遺言の内容を伝えて記憶させます。証人が遺言の内容を読み上げて、遺言者が単にうなずいただけでは口授があったとはいえないと考えられています。
4.口授された遺言の筆記
口授を受けた証人は、口授された遺言の内容を筆記して遺言書を作成します。自分の手で書くことは必須ではなく、タイプライターでもよいと考えられていますが、口授を受ける前に用意したものが有効かは疑問があります。一言一句、口授されたとおり記載する必要はありません。訂正する場合は、各証人が訂正箇所に押印すること、訂正箇所を明らかにする記載をしたうえで署名する必要があります。
5.遺言の読み聞かせ・閲覧
遺言書を作成した証人は、遺言者と他の証人に遺言書を読み聞かせるか、閲覧させて、筆記が正確であることの承認を得る必要があります。この読み聞かせ・閲覧を経て承認された旨の記載は必要ではありません。
6.証人の署名・押印
遺言書には、立ち会った証人の全員が署名・押印をしなければなりません。遺言者本人は署名・押印する必要はありません。
7.遺言の確認
遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認の審判を申し立てる必要があります。申立がなされると、遺言者が生存している場合は、家庭裁判所調査官が遺言者の下へ出向いて危急時遺言の内容が遺言者の真意に基づくものかの調査が行われます。立会証人として遺言書に署名した方は、個別に調査官と面談し、自分に証人適格があることや、遺言が行われた際の状況について事情の説明を求められることがあります。
死亡危急時遺言後の問題
1.6か月の経過
死亡危急時遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、効力がなくなります。たとえば、病状が軽快して自筆証書遺言を作成できるようになった時から遺言者が6か月間生存した時は、死亡危急時遺言の効力は失われます。
2.検認
相続開始後には家庭裁判所での検認が必要です。
※死亡危急時遺言を実際に行う場合、上で述べたこと以外にもさまざまな問題が発生することが予想されます。可能な限り専門家にご相談ください。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【ブログ】大芦渓谷と紅葉
久しぶりに紅葉を見に行こうということで、鹿沼市の大芦渓谷へ行ってきました。
 とても美しく紅葉してました(写真は11月15日)。
とても美しく紅葉してました(写真は11月15日)。
写真の真ん中あたりに車が走れる橋があって、そこからの眺めが有名みたいです。
紅葉もさることながら、渓谷の透き通った清流にも心癒やされました。
紅葉というと日光というイメージでしたが、慎ましやかな大芦渓谷の紅葉もいいものです。
帰りは かぬま まちの駅 で大判焼きを食べて帰りました。
下の写真は渓谷の一画にできたもみじのプールです。写真だとなかなか良さが伝わりませんが。。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【ブログ】佐野ラーメン
今日は天気がよかったですね。
散歩がてら足利フラワーパークへいってきました。
道すがら佐野ラーメンの看板に誘われて寄り道してみると、開店前から行列ができているお店がありました!
森田屋総本店さんでした。チャーシュー麺を注文しました。佐野ラーメンって、甘みのある醤油味がいいですよね。おいしかったです。
足利フラワーパークは、蓮の花が見ごろでした。季節がらあまり花は咲いておりませんでしたが緑がきれいでした。
藤の花が咲く頃にまた行きたいですね。冬場のイルミネーションもなかなかです。
帰りに「道の駅どまんなかたぬま」によりました。このネーミング、おもしろくていいですね。
道の駅はとても盛況でした。駐車場の空きがなかなか見つかりません。最近、道の駅にいくと黒ニンニクをよくみかけますよね。道の駅トレンドでしょうか。
さのまるくんの中にはいって遊べます。これ昔からありますよね。大人ははいっちゃだめかなぁ。。
リフレッシュできました。ということで、事務所に戻ってきてブログ書いています。さぁ、しごと、しごと!

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【ブログ】白馬岳登山~大雪渓をゆく②
 8月3日、白馬岳登山2日目、午前3時30分に起床。身支度を調えて白馬岳山頂を目指す。少し頭痛と吐き気がする。軽く高度障害かも。少し不安だが頭痛薬を飲んで出発することにした。山荘の外へ出ると富山湾の方向に夜景が広がっていた。暗闇の中にぽっかりと浮かんだ光がゆらゆらと動いて見える。昼間には気づかなかった街がそこにある。何とも幻想的な風景だった。山荘からは15分程度で山頂に着いた。ご来光をみるために続々と人が集まってくる。白馬岳の東面は急激に切り立った崖だ。遙か下に流れる沢が広大な樹林帯を縫って走っているのが見える。よく晴れていて遠くにいくつか雲が浮かんでいる。刻々と周囲が明るくなる。景色は千変万化の表上を見せた。どの一瞬も同じではない。そして、日が昇りはじめた。溶けた鉄のようなあかね色の球体が地面から生えてきたようだ。それは嘘みたいに巨大で圧倒的な存在感のある何かだ。太陽が天体であることが実感できる。あっという間に日は昇って周囲の物体を照らしはじめた。山、草、花、朝露、岩、空、雲、風、全てが輝いている。完璧な調和。振り返ると富山湾が空に浮かんでいるように見えた。いつのまにか気分はすっきりしていた。
8月3日、白馬岳登山2日目、午前3時30分に起床。身支度を調えて白馬岳山頂を目指す。少し頭痛と吐き気がする。軽く高度障害かも。少し不安だが頭痛薬を飲んで出発することにした。山荘の外へ出ると富山湾の方向に夜景が広がっていた。暗闇の中にぽっかりと浮かんだ光がゆらゆらと動いて見える。昼間には気づかなかった街がそこにある。何とも幻想的な風景だった。山荘からは15分程度で山頂に着いた。ご来光をみるために続々と人が集まってくる。白馬岳の東面は急激に切り立った崖だ。遙か下に流れる沢が広大な樹林帯を縫って走っているのが見える。よく晴れていて遠くにいくつか雲が浮かんでいる。刻々と周囲が明るくなる。景色は千変万化の表上を見せた。どの一瞬も同じではない。そして、日が昇りはじめた。溶けた鉄のようなあかね色の球体が地面から生えてきたようだ。それは嘘みたいに巨大で圧倒的な存在感のある何かだ。太陽が天体であることが実感できる。あっという間に日は昇って周囲の物体を照らしはじめた。山、草、花、朝露、岩、空、雲、風、全てが輝いている。完璧な調和。振り返ると富山湾が空に浮かんでいるように見えた。いつのまにか気分はすっきりしていた。
 朝日に照らされながら稜線歩きを開始した。360°どこを見ても美しい景色が広がっている。少し歩いては立ち止まり、目を閉じて空を仰いだ。もっと深く、もっとあますことなく、全てを感じ取りたい。早朝の稜線歩きは最高だ。白馬岳山頂から三国境、小蓮華山を通過して、船越の頭へ向かう途中、雷鳥の親子に遭遇した。立山で見たひな鳥よりも一回り大きい雷鳥の子が4羽、一生懸命に草花をつついている。草原を奔放に駆け回って一羽足下までやってきた。雷鳥は本当に愛らしい鳥だ。通りがかった登山者が足を止めて一様にほほ笑んでいた。今日はもう一度くらい雷鳥に会えそうな気がする。そんな予感がした。
朝日に照らされながら稜線歩きを開始した。360°どこを見ても美しい景色が広がっている。少し歩いては立ち止まり、目を閉じて空を仰いだ。もっと深く、もっとあますことなく、全てを感じ取りたい。早朝の稜線歩きは最高だ。白馬岳山頂から三国境、小蓮華山を通過して、船越の頭へ向かう途中、雷鳥の親子に遭遇した。立山で見たひな鳥よりも一回り大きい雷鳥の子が4羽、一生懸命に草花をつついている。草原を奔放に駆け回って一羽足下までやってきた。雷鳥は本当に愛らしい鳥だ。通りがかった登山者が足を止めて一様にほほ笑んでいた。今日はもう一度くらい雷鳥に会えそうな気がする。そんな予感がした。
 船越ノ頭あたりから眼下に白馬大池が見えはじめた。あとで知ったが、船越ノ頭から白馬大池山荘までの登山道はその名も雷鳥坂というそうだ。予感したとおり今度は一羽だけでいる大人の雷鳥を見ることができた。
船越ノ頭あたりから眼下に白馬大池が見えはじめた。あとで知ったが、船越ノ頭から白馬大池山荘までの登山道はその名も雷鳥坂というそうだ。予感したとおり今度は一羽だけでいる大人の雷鳥を見ることができた。
白馬大池山荘から乗鞍岳へ登り、栂池へ下る。この道は安山岩がごろごろしていて、下りはかなり足の筋肉を使った。栂池自然園まで下って、下山は終了した。ここからはロープウェイに乗り、ゴンドラを乗り継いで栂池高原まで下る。11時頃には栂池高原へ到着した。栂の湯という温泉に入ろうと思っていたが営業は12時からとのこと。近くに無料の足湯があったのでそちらで我慢して帰路につく。回送業者に車を運んでおいてもらったので、すぐに車に乗ることができた。
今回は予定通りの山行ができた。充足感と安堵感、美しい風景の記憶、心地よい疲労感を抱えながら帰路についた。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。