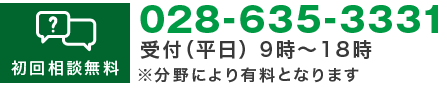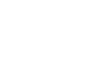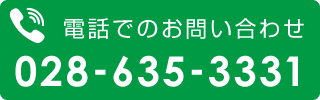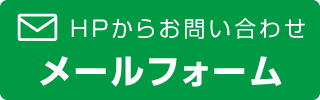Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】新設された「刑の一部の執行猶予」について
<刑の「一部」の執行猶予の創設>
刑事法の分野で、「刑の一部の執行猶予」という制度が新たに創設されました。
本年6月までに施行されることになっています。
刑の一部の執行猶予制度とはどんな制度でしょうか。
昔からある刑の全部の執行猶予制度との違いは何でしょうか。
<刑の全部の執行猶予とは>
犯罪を犯した場合、懲役刑や禁固刑を科せられることがあります。
たとえば懲役2年の刑罰を科せられた場合、その刑罰が執行されると刑務所に収監されることになります。
しかし、懲役2年の刑罰を科せられても、それをすぐには執行しないことがあります。
これが刑の執行猶予というもので、たとえば「懲役2年、ただしその刑の執行を3年間猶予する」といった具合です。
判決が出ても刑務所に収監されることなく、家に帰してもらえます。
その後、新たな犯罪を犯さないで執行猶予期間(先の例では3年間)を満了すると、懲役2年という刑罰を執行されることはなくなります。
懲役2年という刑の全部について執行を猶予するので、刑の全部の執行猶予といいます。
これまでは、執行猶予といえば、制度上、刑の全部の執行猶予しかなかったので、わざわざ「全部の執行猶予」と呼んだりせずに単に「執行猶予」と呼んできました。
今回、一部の猶予という制度ができたので、これと区別するために、従前の執行猶予制度は、刑の全部の執行猶予と呼ぶようになりました。
<刑の一部の執行猶予とは>
刑の一部の執行猶予とは、先の例でいえば、懲役2年のうち、1年は刑を執行し、残り1年は刑の執行を猶予するというものです。
どうなるかといえば、まず、1年について刑の執行を受けるので、刑務所に収監されて1年間をそこで過ごすことになります。ただし、残り1年については、刑の執行を猶予するということなので、1年を経過すると刑務所から出所することになります。
2年の懲役刑を科せられたのに途中で刑務所から出てくるという意味では、仮釈放の制度と似ています。
<何がねらいなのか>
仮釈放の制度があるのに、わざわざ刑の一部執行猶予という制度を創設したのはなぜでしょうか。
一部執行猶予制度のねらいは、薬物犯罪者など再犯率の高い者に十分な保護観察期間を設定することにあります。
薬物犯罪者などの真の更生を図るためには、刑務所を出所した後、病院で治療したり、生活態度を改めたりする必要があります。
保護観察はそのお手伝いをする制度ですが、仮釈放制度下では、仮釈放された時点で残っている刑期しか保護観察に付せませんでした。
先の例でいえば、刑務所で1年を過ごした後、仮釈放で社会に出た後は、保護観察に付せるのは残りの刑期と同じ1年間だけです。
残りの刑期と同じ期間だけでは、その人に本当に必要なサポートが難しいのが実情でした。
刑の一部執行猶予の制度では、残りの期間がどうであるかにかかわらず、1~5年の間で必要なだけ保護観察に付せることができます。
薬物依存が顕著な人で、更生に困難が伴うことが予想される場合などは5年間の保護観察に付したりできるのです。
たとえば、懲役2年、ただし懲役2年のうち懲役1年(刑の一部)については5年間執行を猶予し、その5年の間保護観察に付するとした場合どうなるかといえば、次のようになります。
①まず、刑務所に収監されて1年間服役します。
②1年を経過すると刑の一部執行猶予の効果で出所します。
③出所後、5年間は保護観察によるサポートを受けながら社会生活を送ります。
④5年が経過すると保護観察が終了し、普通に生活することになります。
刑罰の重要な目的の一つに、その犯人が二度と犯罪を犯さないようにするということがあります(再犯の防止)。
これまでの刑事システムでは、薬物犯罪など一部の犯罪については、再犯の防止効果が不十分でした。
刑の一部執行猶予の制度は、再犯の防止のために創設された制度といえるでしょう。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【コラム】特殊な遺言の方式~死亡危急時遺言(臨終遺言)
死亡危急時の遺言とは
遺言にはいくつかの方式がありますが、病気などで生命の危険が迫っている場合に行うものとして死亡危急時遺言(臨終遺言)というものがあります。
死亡危急時遺言のやり方
1.死亡の危急にあること
遺言者に生命の危険が迫っていることが要件です。遺言者が危険が迫っていると自覚していればよく、必ずしも客観的な危険の存在が要求されるわけではありません。ただし、全く危険がないのに本人が危険だと思っているような空想の類いではこの遺言はできません。生命に関わる病気を患っており、その病状が悪化している等、ある程度、客観的な事情は必要だと思われます。
2.3人以上の証人の立ち会い
少なくとも3人の証人が遺言に立ち会わなければなりません。以下にあてはまる方は証人の資格がありません。たとえば、遺言によって財産を譲り受ける方や遺言者の子は、証人になれません。証人適格を欠く者は立ち会い自体を避けるのが無難です。
①未成年者
②推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
③署名できない者(後記6を参照)
④遺言者の口授を理解できない者(後記3を参照)
⑤筆記が正確であることを承認する能力がない者(後記5を参照)
※証人・立会人の欠格事由は、民法974条各号に定められていますが、同条3号の「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」であることが欠格事由になるとの規定は、死亡危急時遺言のような特別方式による遺言には適用がありません。
3.証人の一人への遺言の口授
遺言者は、証人のうちの一人に口頭で遺言の内容を伝えて記憶させます。証人が遺言の内容を読み上げて、遺言者が単にうなずいただけでは口授があったとはいえないと考えられています。
4.口授された遺言の筆記
口授を受けた証人は、口授された遺言の内容を筆記して遺言書を作成します。自分の手で書くことは必須ではなく、タイプライターでもよいと考えられていますが、口授を受ける前に用意したものが有効かは疑問があります。一言一句、口授されたとおり記載する必要はありません。訂正する場合は、各証人が訂正箇所に押印すること、訂正箇所を明らかにする記載をしたうえで署名する必要があります。
5.遺言の読み聞かせ・閲覧
遺言書を作成した証人は、遺言者と他の証人に遺言書を読み聞かせるか、閲覧させて、筆記が正確であることの承認を得る必要があります。この読み聞かせ・閲覧を経て承認された旨の記載は必要ではありません。
6.証人の署名・押印
遺言書には、立ち会った証人の全員が署名・押印をしなければなりません。遺言者本人は署名・押印する必要はありません。
7.遺言の確認
遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認の審判を申し立てる必要があります。申立がなされると、遺言者が生存している場合は、家庭裁判所調査官が遺言者の下へ出向いて危急時遺言の内容が遺言者の真意に基づくものかの調査が行われます。立会証人として遺言書に署名した方は、個別に調査官と面談し、自分に証人適格があることや、遺言が行われた際の状況について事情の説明を求められることがあります。
死亡危急時遺言後の問題
1.6か月の経過
死亡危急時遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6か月間生存するときは、効力がなくなります。たとえば、病状が軽快して自筆証書遺言を作成できるようになった時から遺言者が6か月間生存した時は、死亡危急時遺言の効力は失われます。
2.検認
相続開始後には家庭裁判所での検認が必要です。
※死亡危急時遺言を実際に行う場合、上で述べたこと以外にもさまざまな問題が発生することが予想されます。可能な限り専門家にご相談ください。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【コラム】離婚調停が終了したら、いつまでに離婚裁判を起こすべきか?
離婚調停が終了後、相当期間が経過した場合にも離婚裁判を提起できるのでしょうか?
本当は明確な答えはありませんが、ずばりいえば、
1年以内ならまず大丈夫
1年半を超えるあたりから微妙
2年を超えると再度の調停が必要なケースが多い
のかなと思います。
前提として、離婚裁判を提起しようとする場合、先に離婚調停を経ている必要があります(家事事件手続法257条)。「裁判の前に調停を置く」という意味で「調停前置主義」と呼ばれています。
どうしてこのような原則が定められているのか?それは、家庭の問題は裁判で争うよりも当事者が話し合って円満に解決した方がよいと考えられているからです。
そこで、協議離婚ができない場合には離婚調停を申し立てることになります。調停がまとまらないと、調停は不成立か取下げによって終了します。ただし、調停が終了しても自動的に裁判に移行するわけではありません。離婚の裁判を開始するには、訴状を裁判所に提出する必要があります。いつ離婚裁判を開始するかは当事者にイニシアティブが与えられているのです。結果、調停が終了してから離婚の裁判を開始するまでの期間は事案ごとに異なります。人によっては事情があって、すぐには裁判ができない場合もあるでしょう。しかし、離婚問題では夫婦が現時点でどのような状態にあるのかが重要です。たとえば、調停時には別居していた夫婦がその後別居を解消することもあり得ます。その場合、婚姻が破綻しているのかどうかは現在の状況を前提に判断しなければなりません。したがって、はじめの調停から相当な期間が経過してしまった場合は改めて調停を行う必要があると考えられています。
では、どの程度の期間が経過したら再度の調停が必要となるのでしょうか。これについては、ケースバイケースで判断されるので明確な答えはありません。あえて言えば、冒頭で述べたとおり、1年以内ならまず大丈夫、1年半を超えるあたりから微妙で、2年を超えると再度の調停が必要なケースが多くなるのではないかと思われます。
ちなみに、調停を前置しないでいきなり離婚訴訟を提起したとしてもペナルティが課せられることはありません。離婚訴訟も当然に却下されるわけではなくて調停に回されることになります(家事事件手続法257条2項)。とはいえ、調停のために費やす労力は相当なものです。精神的にも疲弊するので、できれば1回で済ませたいと思われる方は多いと思います。そうであれば、調停が終了してから1年以内に離婚訴訟を提起することをおすすめします。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【コラム】親権の争いでは母親が有利というのは本当か?
離婚をする夫婦に未成年の子どもがいる場合、親のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。どちらの親も親権を主張して譲らない場合、通常、離婚の裁判で決めることになります。
親権者の指定について争われる場合、「母親が有利というのは本当ですか?」との質問を受けることがあります。
私はこのようなご質問を受けた場合、「母親というだけで有利ということはありませんが、母親が親権者に指定されることが多いと思います。」とお答えしています。じゃあ結局、母親が有利なのか?この謎を解くためには親権者の指定に関する判断基準を知っておく必要があります。
親権者の指定が争われた場合、裁判所はどういう基準を用いて判断を下すのでしょうか?その基準は、「子の利益」だと言われています。子の利益の中で一番重要なのは、子どもが精神的・肉体的に問題なく成長できることです。どちらの親と一緒に暮らした方がすくすく成長できるのか?そのことを諸事情を総合考慮して判断します。こうして諸事情を考えてケースバイケースで判断することになるのですが、諸事情の中でも特に道しるべとなる事情がいくつかあると言われています。
そのひとつが、「母親優先の原則」と言われてきたものです。
これは、特に乳幼児については、母親の存在が不可欠であるとして母親を親権者に指定するべきという考えです。これが本当だとすれば、父親が親権者に指定されることはほとんどないということになりそうです。しかし、心理学的には子どもにとって重要な存在は、「母親としての役割をはたす人間」であって、その役割を果たせるのは生物学上の母親に限らないと考えられています。子どもは、はじめに親としての役割を果たした人に対して愛着を形成します。したがって、育児を積極的に行ってきた父に対して子が愛着を形成していることは充分にあり得ることです。そこで、最近では生物学上の母親を優先するのではなく、母性的な役割を果たす者との関係を重視すべきであるといわれるようになりました。そのため、「母親優先の原則」ではなく「母性優先の原則」と呼ばれるようになってきました。なお、心理学上、親から子に対する情緒的な結びつきを「絆」といい、子から親に対する情緒的な結びつきを「愛着」と呼ぶようです。
また、「監護の継続性」という基準も重要です。
これは、子にとっては、親と子の精神的な結びつき(絆と愛着)が重要であるから、このような結びつきを断絶させるような監護者の変更はするべきではないという考え方です。したがって、夫婦が別居した後、幼い子が片方の親に継続的に監護されており、親子間に絆と愛着が形成されている場合、そのままの状態を維持するように親権者の指定を行うべきということになります。
ほかにもいくつか指標とされている基準がありますが、乳幼児の親権者指定の問題では、「母性優先の原則」と「監護の継続性」が重要な指標となるのは間違いありません。そこで、父親と母親のどちらが母性的な役割を果たしてきたのか(母性優先の原則)、父親と母親のどちらが子の監護を継続しているのか(監護の継続性)が問題になります。事案によっては、そのいずれもが父親であるということもあり得ます。したがって、「親権の争いでは母親が有利というのは本当か?」という問いに対しては、「母親というだけで有利ということはありません。」とお答えすることになります。ただし、女性の社会進出が進み男性の育児参加が珍しくなくなった現在でも、なお母親が子にとって第一の養育者であることが多いと思います。その場合、やはり母親が継続的に監護を続けていることが多いと思います。そのため、結果的に母親を親権者として指定すべき事案が多くなります。したがって、「母親が親権者として指定されることが多いと思います。」という回答になります。
以上に述べたことは、あくまで一般的な話です。事案の内容は千差万別であって、簡単に結論がでるようなものはほとんどありません。お悩みの際は、家事事件に熱心に取り組んでいる弁護士に相談するのがよいでしょう。親権者の指定は、子どもの人生にとってとても重要な問題です。子どもはまだ自分で自分の人生を選ぶ準備ができていません。そのため、子の利益を第一に考えて親権者を指定しなければなりません。父親は、「親権を争ってもどうせ母親には勝てない。」と早々に親権を放棄すべきではありません。父親も母親も、離婚する前にどちらが子の親権者となるのがよいのか真剣に考えてみるべきです。できれば、夫婦でよく話し合うべきでしょう。
私は、時には父親から相談を受けたり、母親から相談を受けたりします。通常の案件ではいつも依頼者の利益を第一に考えるのですが、離婚事件、特に親権者の指定が関連する場合は、どうしてもお子さんの将来のことを考えてしまいます。依頼者様の意向を尊重するのは当然ですが、お子様たちの幸せに少しでも貢献したいという気持ちで取り組んでいます。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【コラム】ワールドカップに特措法が定められていたのを御存知ですか。
ブラジルワールドカップもそろそろ予選が終わりそうですね。
しばらくサッカーを見ていなかったのですが、今大会の日本の代表選手には海外で活躍している選手がたくさんいて頼もしく感じられました。
ただ、睡眠不足を覚悟でテレビ観戦したコロンビア戦で予選敗退が決まってしまって寂しいです。決勝ラウンドでの勇姿を見たかった。コロンビア戦は、勝利への意思がはっきりと見て取れて前半は期待が膨らみましたが、終わってみると気持ちよいくらい完敗でしたね。この悔しさを糧に次に繋げたいところです。
今大会、私が注目している選手はメッシとネイマールです。というか普通、サッカーを見ている人は誰でも注目しているスーパースターですよね。この2選手のプレーを見ていると、とにかく、速くて、うまくて、ついていけない、という感じがしました。言い古された表現ですが、来ると分かっていても止められないといったところでしょうか。もどかしく感じることが多いサッカーの試合にあって、この二人は圧倒的で爽快な瞬間を見せてくれます。だからスター選手と呼ばれるのですね。
とここで、少し法律のお話しをすると、2002年の日韓共同開催のワールドカップに関連してある特別措置法が制定されていることに気付きました。その名も「平成14年ワールドカップサッカー大会特別措置法」(平成10年5月27日公布)というものです。特別措置法というと、テロ対策特別措置法のように厳めしいイメージがあるので、ワールドカップと特別措置法ってどこか不思議な組合せです。立法技術的には特措法となるのが自然なのでしょうが。。この法律は、わずか4条から成り立っていて、ワールドカップサッカー大会組織委委員会への寄付目的で寄付金付郵便葉書を発行できることや、国際サッカー連盟から支払われる報酬(大会の試合の審判員の報酬など)を非課税とすることを定めています。この法律以外にもワールドカップのために整備された法令はあるのかもしれませんが、偶然見つけたので紹介させていただきました。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。