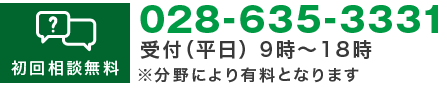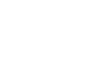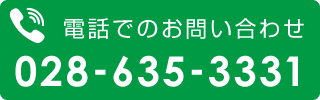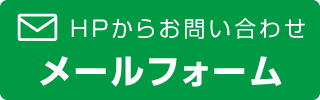Author Archive
【ブログ】白馬岳登山~大雪渓をゆく
 前回、立山ではじめて雪渓を体験した。アイゼンを装着して雪の斜面を登る楽しさを知った。そこで、今度は白馬岳(しろうまだけ)の大雪渓に挑戦することにした。せっかくなので本格的なアイゼンをと思い、宇都宮の好日山荘に問い合わせるとグリベル製のアイゼンが1個だけあるとのことだった。早速、好日山荘へ行き、グリベル製の12本爪アイゼンを購入した。これで準備は万端となった。
前回、立山ではじめて雪渓を体験した。アイゼンを装着して雪の斜面を登る楽しさを知った。そこで、今度は白馬岳(しろうまだけ)の大雪渓に挑戦することにした。せっかくなので本格的なアイゼンをと思い、宇都宮の好日山荘に問い合わせるとグリベル製のアイゼンが1個だけあるとのことだった。早速、好日山荘へ行き、グリベル製の12本爪アイゼンを購入した。これで準備は万端となった。
8月1日夜に白馬村へ移動し、22時頃にホテルへチェックインできた。ホテルは嬉しいことに源泉掛け流しの温泉だった。大人が4人入ると一杯になる程度の狭い浴槽だったが、そのことがかえって旅情を誘った。温泉の質も最高だった。
8月2日、朝4時30分に起床。身支度を調えて、白馬村にある公共駐車場へ移動。駐車場からは、自動車の回送業者の方の運転で登山口である猿倉荘まで送ってもらった。朝6時くらいの猿倉山荘前は登山客で賑わっていた。登山計画書を提出していざ出発。
 よく晴れている。1時間ほど歩くと、白馬尻小屋に到着。小屋の前を沢の水が勢いよく流れている。その上流の方をみると、沢が途中から雪に変わっている。これが今回のメイン、大雪渓だ。白馬尻小屋で大雪渓を眺めつつ、ローソンで買った菓子パンを2つ食べた。白馬尻小屋から15分ほど歩くと大雪渓に到着。ザックからアイゼンを引っ張り出して装着。事前に何度も着脱訓練をしておいたのでスムーズに装着できた。いよいよ大雪渓を登りはじめる。幅100メートル、全長3.5キロに及ぶ大雪渓。思いっきり感動しながら歩き出した。当日は、登山客がとても多くて、大雪渓上はいわゆる「蟻の行列」状態であった。ただ、渋滞というほどでもなく、気持ちよく歩を進めることができた。雪渓上の空気は冷たかったが、歩いていると暑くなるのでちょうどよかった。雪渓上にはたくさんの石や岩が転がっていた。これらは全て落石とのこと。中には大きな岩もある。これが音もなく転がってくる光景は見てみたい気もするが、ぶつかればただでは済まない。
よく晴れている。1時間ほど歩くと、白馬尻小屋に到着。小屋の前を沢の水が勢いよく流れている。その上流の方をみると、沢が途中から雪に変わっている。これが今回のメイン、大雪渓だ。白馬尻小屋で大雪渓を眺めつつ、ローソンで買った菓子パンを2つ食べた。白馬尻小屋から15分ほど歩くと大雪渓に到着。ザックからアイゼンを引っ張り出して装着。事前に何度も着脱訓練をしておいたのでスムーズに装着できた。いよいよ大雪渓を登りはじめる。幅100メートル、全長3.5キロに及ぶ大雪渓。思いっきり感動しながら歩き出した。当日は、登山客がとても多くて、大雪渓上はいわゆる「蟻の行列」状態であった。ただ、渋滞というほどでもなく、気持ちよく歩を進めることができた。雪渓上の空気は冷たかったが、歩いていると暑くなるのでちょうどよかった。雪渓上にはたくさんの石や岩が転がっていた。これらは全て落石とのこと。中には大きな岩もある。これが音もなく転がってくる光景は見てみたい気もするが、ぶつかればただでは済まない。
雪渓の終着点、葱平(ねぶかっぴら)に到着。白い雪渓、クリーム色の山肌、青い空、緑のお花畑。夏の強い日差しに照らされて、下界では見れないような鮮やかな色が浮かび上がっていた。その後、小さな雪渓をトラバースした。距離は短いが滑り落ちるとやばそうだ。頂上手前にはお花畑が広がっていた。貴重な高山植物が群生している。高山植物を守っている白馬グリーンパトロール隊の隊員とすれ違った。
 白馬岳頂上宿舎でトイレ休憩を入れ、20分ほど登り、本日の目的地である白馬山荘に到着した。確か12時を少し過ぎた頃だった。レストランでおでんと生ビール注文した。時間がたっぷりあるので、山荘前のベンチに寝そべって眼前の旭岳を眺めながら夕方までぼーっとしていた。山荘はとても混み合っていて、1畳分のスペースに2人が寝なければならない状態だった。もっと混んでいる時は1畳のスペースに3人寝てもらうこともあるとのこと。うへーっと思う以前に、それって可能なの?と思ってしまった。山小屋は混んでなければ最高なのだが。今度はテントを担いでこよう。16時過ぎからどしゃ降りの雨になった。雨が降ると肌寒いくらいだ。夕食を食べて19時前には布団に潜り込んだ。疲れていたが眠れたのはおそらく0時頃だったと思う。
白馬岳頂上宿舎でトイレ休憩を入れ、20分ほど登り、本日の目的地である白馬山荘に到着した。確か12時を少し過ぎた頃だった。レストランでおでんと生ビール注文した。時間がたっぷりあるので、山荘前のベンチに寝そべって眼前の旭岳を眺めながら夕方までぼーっとしていた。山荘はとても混み合っていて、1畳分のスペースに2人が寝なければならない状態だった。もっと混んでいる時は1畳のスペースに3人寝てもらうこともあるとのこと。うへーっと思う以前に、それって可能なの?と思ってしまった。山小屋は混んでなければ最高なのだが。今度はテントを担いでこよう。16時過ぎからどしゃ降りの雨になった。雨が降ると肌寒いくらいだ。夕食を食べて19時前には布団に潜り込んだ。疲れていたが眠れたのはおそらく0時頃だったと思う。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【ブログ】はじめての立山登山(2日目)
 2日目の朝、外を見ると空が晴れていた。雨雲ズームレーダーを見ても近くに雲は見当たらない。昨夜の予報では今日も大荒れのはず。だがどうみても穏やかな天気だ。ホテル立山から室堂山展望台までなら往復でも2時間で行けそうだ。ということで急遽、登山をすることにした。片道1時間くらいなので、売店で肩掛けカバンを購入し、レインウェアと防寒着、アクエリアス1本を詰め込んで出発だ。
2日目の朝、外を見ると空が晴れていた。雨雲ズームレーダーを見ても近くに雲は見当たらない。昨夜の予報では今日も大荒れのはず。だがどうみても穏やかな天気だ。ホテル立山から室堂山展望台までなら往復でも2時間で行けそうだ。ということで急遽、登山をすることにした。片道1時間くらいなので、売店で肩掛けカバンを購入し、レインウェアと防寒着、アクエリアス1本を詰め込んで出発だ。
登山道の入口まで行くとまた雪の斜面が広がっている。昨日、体験済みなので今日は気持ちに余裕がある。近くの施設の人だろうか、男性が2人、ツルハシとスコップで階段を作ってくれていた。「ここから先はアイゼンなしでもいけますか?」と聞くと、「行けるよ」とのこと。もちろん、自己責任で判断しなければならないが、その言葉に安心して登っていくことにした。早朝のさわやかな空気に包まれながら、踏みしめる雪の感触が心地よい。少し登ると霧が出てきたが、流れている霧なので10分程度で視界は開ける。ちょうどウォーミングアップが済んだ頃に室堂山展望台に到着。山と高原地図には、360°のパノラマと書いてあったが、見わたす限りの霧だった。
まだ時間もあるし、お隣の浄土山まで行ってみることにした。室堂展望台から雪渓を横切り浄土山の山頂を目指す。浄土山の頂上までは20分くらいの軽い岩場になっていた。ところどころ岩をつかみながら、登っていく。頂上に近づくにつれ鼓動が早くなっていくのが分かった。浄土山の標高は2831メートルで空気が薄いせいだと思う。頂上らしきところへ着いたが、もう少し探検してみたいのでさらに歩を進めると小屋が見えた。行ってみると、富山大学の研究所と書いてある。無人のようだ。ここで気象の研究でもしてるのだろうか。
一休みの後、来た道を帰る。すると、登山道に雷鳥の親子を見つけた。雷鳥を見るのはこれで2度目。ちいさな雛が5羽、母親のあとを着いていく。凄い足の回転で、置いてけぼりにならないようにがんばっている姿がとても健気だ。室堂付近にあった情報プレートによれば雷鳥は3000羽程度しかいないらしい。人を怖がらないところが、イルカのように妙な親近感を呼び起こす。昨日は途中下山することになって少し落ち込んだけど、立山に来てよかった。雷鳥さん、ありがとう。
そして、下山後、黒部ダムへ。晴れていたので放水の水しぶきにレインボーがあらわれた。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【ブログ】はじめての立山登山(1日目)
7月19日から21日にかけて立山・黒部へ行ってきました。「山と渓谷」7月号の記事と好きなお酒の一つである「銀嶺立山」に誘われて立山へ行ってみようと思ったのでした。
しかし、気になるのは天気のこと。梅雨時に3000メートル近い高山に登るのは自分の力量からしたら無謀だと思われました。7月19日頃には梅雨明けしていればいいのに。そう思って、携帯に届く山の天気予報を毎日チェックしていましたが予報は悪化するばかりです。「ゲリラ豪雨に注意?まぁいいか。登山口まで行ってから撤退してもいいではないか。」と自分に言い聞かせて18日の夜に富山入りしました。
翌19日早朝からいよいよ登山開始です。立山には室堂という場所から登りはじめます。一般車両が乗り入れ不可なので、立山駅から立山ケーブルカー、立山高原バスを乗りついで室堂へ向かいました。立山駅にはツバメがたくさんいて、その愛らしい姿が登山の不安を和らげてくれました。
早朝の室堂にはテンションの高い登山者がひしめき合っていて、マラソン大会前のような熱気に包まれていました。空は曇天で、霧は濃く、いつ雨が降ってきてもおかしくない様子でしたが、午前中はなんとか天気が持つと聞いていたので登山を開始しました。霧が濃くて視界不良でしたが、室堂から雷鳥沢キャンプ場までは石畳の道で余裕でした。
ところが雷鳥沢キャンプ場を過ぎて程なくして雪の急斜面が表れたのです。「これが雪渓ってやつだろうか。」さっきまで石畳の上をのんびりした気持ちで歩いていたので不意打ちを食らった形でした。かなりの急斜面に見えて、転んだらどこまでも滑り落ちていく気がしました。とりあえず、チョコバーを一本食べて気を落ち着かせました。見ると、なんの装備もなしに普通に登っていく人もいます。しかし、私は念のために持ってきたアイゼンを装着することにしました。はじめてのアイゼンです。ばっちりグリップが効きました。装備の効果に少し感動しながら雪の斜面をぐいぐい登っていきました。
しかし斜面をひと登りしたところで問題が発生しました。どっちへ進めばよいか分からないのです。雪が登山道を覆ってしまっているようでどれが道なのか分かりません。先にいった人たちの足跡も見えません。おまけに濃い霧がでてきて、今歩いてきた場所が見えなくなっています。追い打ちをかけるように遠くでゴーンと雷のような音が聞こえました。山で雷に遭遇するのは本当に怖いです。自分が初歩的なルートファインディングもできないことが分かりました。地図は携行していましたが、焦ってからはじめて地図を見てもどうにもならなかったです。
「よし、下山しよう。」そう決断して歩いてきた方向へ戻りました。少し歩くと後からやってきた登山者に会えました。自分が道に迷った時間は10分程度だったと思いますが、人に会えた時は本当に安心しました。
帰りに雷雨に遭いやっとの思いで室堂へ戻りました。
結局19日は目的地の山小屋へ到着することができず、苦い思いと言いようのない安堵感 を感じながらホテル立山で眠りました。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【コラム】離婚調停が終了したら、いつまでに離婚裁判を起こすべきか?
離婚調停が終了後、相当期間が経過した場合にも離婚裁判を提起できるのでしょうか?
本当は明確な答えはありませんが、ずばりいえば、
1年以内ならまず大丈夫
1年半を超えるあたりから微妙
2年を超えると再度の調停が必要なケースが多い
のかなと思います。
前提として、離婚裁判を提起しようとする場合、先に離婚調停を経ている必要があります(家事事件手続法257条)。「裁判の前に調停を置く」という意味で「調停前置主義」と呼ばれています。
どうしてこのような原則が定められているのか?それは、家庭の問題は裁判で争うよりも当事者が話し合って円満に解決した方がよいと考えられているからです。
そこで、協議離婚ができない場合には離婚調停を申し立てることになります。調停がまとまらないと、調停は不成立か取下げによって終了します。ただし、調停が終了しても自動的に裁判に移行するわけではありません。離婚の裁判を開始するには、訴状を裁判所に提出する必要があります。いつ離婚裁判を開始するかは当事者にイニシアティブが与えられているのです。結果、調停が終了してから離婚の裁判を開始するまでの期間は事案ごとに異なります。人によっては事情があって、すぐには裁判ができない場合もあるでしょう。しかし、離婚問題では夫婦が現時点でどのような状態にあるのかが重要です。たとえば、調停時には別居していた夫婦がその後別居を解消することもあり得ます。その場合、婚姻が破綻しているのかどうかは現在の状況を前提に判断しなければなりません。したがって、はじめの調停から相当な期間が経過してしまった場合は改めて調停を行う必要があると考えられています。
では、どの程度の期間が経過したら再度の調停が必要となるのでしょうか。これについては、ケースバイケースで判断されるので明確な答えはありません。あえて言えば、冒頭で述べたとおり、1年以内ならまず大丈夫、1年半を超えるあたりから微妙で、2年を超えると再度の調停が必要なケースが多くなるのではないかと思われます。
ちなみに、調停を前置しないでいきなり離婚訴訟を提起したとしてもペナルティが課せられることはありません。離婚訴訟も当然に却下されるわけではなくて調停に回されることになります(家事事件手続法257条2項)。とはいえ、調停のために費やす労力は相当なものです。精神的にも疲弊するので、できれば1回で済ませたいと思われる方は多いと思います。そうであれば、調停が終了してから1年以内に離婚訴訟を提起することをおすすめします。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【コラム】親権の争いでは母親が有利というのは本当か?
離婚をする夫婦に未成年の子どもがいる場合、親のどちらか一方を親権者に指定しなければなりません。どちらの親も親権を主張して譲らない場合、通常、離婚の裁判で決めることになります。
親権者の指定について争われる場合、「母親が有利というのは本当ですか?」との質問を受けることがあります。
私はこのようなご質問を受けた場合、「母親というだけで有利ということはありませんが、母親が親権者に指定されることが多いと思います。」とお答えしています。じゃあ結局、母親が有利なのか?この謎を解くためには親権者の指定に関する判断基準を知っておく必要があります。
親権者の指定が争われた場合、裁判所はどういう基準を用いて判断を下すのでしょうか?その基準は、「子の利益」だと言われています。子の利益の中で一番重要なのは、子どもが精神的・肉体的に問題なく成長できることです。どちらの親と一緒に暮らした方がすくすく成長できるのか?そのことを諸事情を総合考慮して判断します。こうして諸事情を考えてケースバイケースで判断することになるのですが、諸事情の中でも特に道しるべとなる事情がいくつかあると言われています。
そのひとつが、「母親優先の原則」と言われてきたものです。
これは、特に乳幼児については、母親の存在が不可欠であるとして母親を親権者に指定するべきという考えです。これが本当だとすれば、父親が親権者に指定されることはほとんどないということになりそうです。しかし、心理学的には子どもにとって重要な存在は、「母親としての役割をはたす人間」であって、その役割を果たせるのは生物学上の母親に限らないと考えられています。子どもは、はじめに親としての役割を果たした人に対して愛着を形成します。したがって、育児を積極的に行ってきた父に対して子が愛着を形成していることは充分にあり得ることです。そこで、最近では生物学上の母親を優先するのではなく、母性的な役割を果たす者との関係を重視すべきであるといわれるようになりました。そのため、「母親優先の原則」ではなく「母性優先の原則」と呼ばれるようになってきました。なお、心理学上、親から子に対する情緒的な結びつきを「絆」といい、子から親に対する情緒的な結びつきを「愛着」と呼ぶようです。
また、「監護の継続性」という基準も重要です。
これは、子にとっては、親と子の精神的な結びつき(絆と愛着)が重要であるから、このような結びつきを断絶させるような監護者の変更はするべきではないという考え方です。したがって、夫婦が別居した後、幼い子が片方の親に継続的に監護されており、親子間に絆と愛着が形成されている場合、そのままの状態を維持するように親権者の指定を行うべきということになります。
ほかにもいくつか指標とされている基準がありますが、乳幼児の親権者指定の問題では、「母性優先の原則」と「監護の継続性」が重要な指標となるのは間違いありません。そこで、父親と母親のどちらが母性的な役割を果たしてきたのか(母性優先の原則)、父親と母親のどちらが子の監護を継続しているのか(監護の継続性)が問題になります。事案によっては、そのいずれもが父親であるということもあり得ます。したがって、「親権の争いでは母親が有利というのは本当か?」という問いに対しては、「母親というだけで有利ということはありません。」とお答えすることになります。ただし、女性の社会進出が進み男性の育児参加が珍しくなくなった現在でも、なお母親が子にとって第一の養育者であることが多いと思います。その場合、やはり母親が継続的に監護を続けていることが多いと思います。そのため、結果的に母親を親権者として指定すべき事案が多くなります。したがって、「母親が親権者として指定されることが多いと思います。」という回答になります。
以上に述べたことは、あくまで一般的な話です。事案の内容は千差万別であって、簡単に結論がでるようなものはほとんどありません。お悩みの際は、家事事件に熱心に取り組んでいる弁護士に相談するのがよいでしょう。親権者の指定は、子どもの人生にとってとても重要な問題です。子どもはまだ自分で自分の人生を選ぶ準備ができていません。そのため、子の利益を第一に考えて親権者を指定しなければなりません。父親は、「親権を争ってもどうせ母親には勝てない。」と早々に親権を放棄すべきではありません。父親も母親も、離婚する前にどちらが子の親権者となるのがよいのか真剣に考えてみるべきです。できれば、夫婦でよく話し合うべきでしょう。
私は、時には父親から相談を受けたり、母親から相談を受けたりします。通常の案件ではいつも依頼者の利益を第一に考えるのですが、離婚事件、特に親権者の指定が関連する場合は、どうしてもお子さんの将来のことを考えてしまいます。依頼者様の意向を尊重するのは当然ですが、お子様たちの幸せに少しでも貢献したいという気持ちで取り組んでいます。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【コラム】ワールドカップに特措法が定められていたのを御存知ですか。
ブラジルワールドカップもそろそろ予選が終わりそうですね。
しばらくサッカーを見ていなかったのですが、今大会の日本の代表選手には海外で活躍している選手がたくさんいて頼もしく感じられました。
ただ、睡眠不足を覚悟でテレビ観戦したコロンビア戦で予選敗退が決まってしまって寂しいです。決勝ラウンドでの勇姿を見たかった。コロンビア戦は、勝利への意思がはっきりと見て取れて前半は期待が膨らみましたが、終わってみると気持ちよいくらい完敗でしたね。この悔しさを糧に次に繋げたいところです。
今大会、私が注目している選手はメッシとネイマールです。というか普通、サッカーを見ている人は誰でも注目しているスーパースターですよね。この2選手のプレーを見ていると、とにかく、速くて、うまくて、ついていけない、という感じがしました。言い古された表現ですが、来ると分かっていても止められないといったところでしょうか。もどかしく感じることが多いサッカーの試合にあって、この二人は圧倒的で爽快な瞬間を見せてくれます。だからスター選手と呼ばれるのですね。
とここで、少し法律のお話しをすると、2002年の日韓共同開催のワールドカップに関連してある特別措置法が制定されていることに気付きました。その名も「平成14年ワールドカップサッカー大会特別措置法」(平成10年5月27日公布)というものです。特別措置法というと、テロ対策特別措置法のように厳めしいイメージがあるので、ワールドカップと特別措置法ってどこか不思議な組合せです。立法技術的には特措法となるのが自然なのでしょうが。。この法律は、わずか4条から成り立っていて、ワールドカップサッカー大会組織委委員会への寄付目的で寄付金付郵便葉書を発行できることや、国際サッカー連盟から支払われる報酬(大会の試合の審判員の報酬など)を非課税とすることを定めています。この法律以外にもワールドカップのために整備された法令はあるのかもしれませんが、偶然見つけたので紹介させていただきました。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。
【お知らせ】ホームページをリニューアルしました。
栃のふたば法律事務所
当事務所のホームページをリニューアルしました。
ホームページを通じて、当事務所の雰囲気や弁護士の人柄を少しでもお伝えできれば幸いです。

「栃のふたば法律事務所」は、栃木県宇都宮市にある地域密着型の法律事務所です。栃木県の皆さまをサポートします。
離婚・相続といったご家庭の法律問題、不当要求や労使紛争などの企業の法律問題、さらに交通事故やインターネット上の誹謗中傷、刑事弁護といった身近なトラブルまで、幅広い分野に対応。
当事務所は、法律の専門家として、相談者一人ひとりの人生に寄り添い、法的な見解だけでなく、現実的な解決策も提示します。
質の高いリーガルサービスを提供するため、リサーチにも力を入れています。
まずはお気軽にお問い合わせください。皆さまの抱える問題に、誠実かつ全力で向き合います。